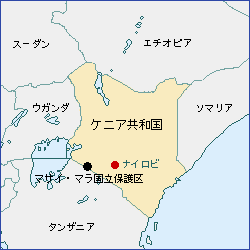 ケニア地図 |
片言の日本語で話しかけてくる4人くらいのオヤジの話を一通り聞く。安い。だが白昼とはいえタクシーは一度乗ったら降りることはできないので十分に注意する必要がある。で信用できるタクシーとなればやはりオフィシャルのエアポートタクシーだろう、ということでカウンターで聞いてみる。外の危ない奴らよりは高いが、少し割り引いてくれた。係員に案内されてタクシーへ。さっき声をかけてきたオヤジたちは必死に食い下がる。
「それは高いって。こっちの方が断然安いぞ!」
僕は無視して車に乗り込んだ。今まで空港タクシーは値切って値切ってというスタンスだったが、ナイロビでは金で身の安全を買わなければならない。値切った挙句に何をされるのか。安すぎる値段の裏にある落とし穴。空港からナイロビ市内まで17km。
ナイロビは南緯1.2度(赤道から約140km南)、海抜1700mに位置するケニアの首都である。標高が高いため1年中通じて初夏のような気候で、平均気温が17.5℃。エクアドルのアンデス山中にあるキトやクエンカといった主要都市と同じ状況だ。”標高高くて赤道直下”=”1年中変わらない過ごしやすい気候”という方程式である。確かに涼しい。昼の最高気温で20℃くらいか。”ナイロビ”とは、マサイ語の「エンカレ・ナイロビ」(=冷たい水)から来たと言われ、アフリカとしては水がきれいで豊富な街だそうである。
ケニアの予定において、ナイロビはたったの一日。今日、大晦日だけ。なぜ私ともあろう者がこんなにもナイロビにビビッているのか。ご説明しよう。僕は愛読書『地球の歩き方』を計20冊ほど持っているが、ナイロビの記述は文句なくビビるのに十分である。間違いなく僕が持っている『歩き方』の中では一番危ない街である。以下のような記述が紙面狭しと並んでいる。
『本来なら、町をいろいろ紹介し、歩いてもらいたいのだが、ナイロビの治安は昼夜を問わず著しく悪化しているため、タウン中心部以外は昼間でも決して歩かないでほしい。』
 ナイロビ市内中心部、ケニヤッタ通り沿い |
 |
 |
 ホテルエンバシーの気さくな従業員ベンソン(左) |
 これまた気さくな従業員の若者、仕事中なのに昼間から ウィスキー飲んでいて、僕も少し分けてもらった(笑) 話してみるとかなり酔ってる感じだったけど、 顔黒いから酔ってるのがさっぱり分からない(笑) |
 夕食、ニャマチョマもどき |
『ここではバックパッカーも(強盗の)ターゲットになっている。(中略)ともかくナイロビでは、用事もないのに出歩くことは絶対避けてほしい。』
『ダウンタウンへは決して行ってはいけない。』
こういった記述がナイロビのページを埋め尽くしている。『地球の歩き方』ともあろう本が、「歩くな」と言っているのだ。これを読んでビビらない奴がいるか?いったいどういう街だよ、ナイロビって?外を歩けない?そういえば、椎名誠の怪しい探検隊も、20年近くも前の話だが、ナイロビの夜に強盗に遭った。以上の説明を聞けば、読者諸兄も、”無謀さ”が持ち味の僕なのに、なぜこんなにも今回の旅行記には怯えというか臆病さが全編に渡って通底しているのかという理由を少しは理解いただけることと思う。少なくともダルエスサラームとナイロビの記述は非常に危険な印象を僕に与えた。今までの旅行にはなかったビビリがこの旅行記に満載されていることは恥ずかしい限りであるが仕方ない。いや、むしろ今までの旅行があまりにも怖いもの知らず過ぎたのかもしれない。運の良さだけで切り抜けてこれただけなのかも。いや、僕の中でのビビリの発生については、2005年12月の中米ホンジュラスはテグシガルパでの強盗未遂事件を僕が経験したことなしには語れない(よって執筆急ぎます)。まぁ何でもいいや。
僕が泊まることにしたホテル・エンバシーに、一人の日本人バックパッカーの若者が泊まっていた。彼は見たところ大学生風情で、痩せ型で坊主頭。エチオピアからバスでナイロビに入って今日で3日目だという。彼は絶対に行ってはならないとされているダウンタウンに行ってきたそうである。というのはエチオピアからのバスで一緒になった別の日本人バックパッカーがダウンタウンの日本人安宿に泊まっているのだそうだ。
「えっ、ダウンタウンに行ったの?」
「何も身に着けずに歩けば、それほど危ない感じはしないです。」
「へえぇ。」
「ただ今日は日曜だからか、街にいる警官の数が少ないですね。昨日とかおとといは警官がたくさんいたから結構安心でしたけど。」
「そうか、やっぱりよっぽど治安が悪いんだな。」
「ダウンタウンで僕らの共通の友達、マレー系のオーストラリア人の女の子なんですけど、今朝強盗にやられました。」
「えっ、やっぱダウンタウンは危ないんだ。」
「宿からわずか2分くらいの、すぐそこのバス停に行くまでの間にやられたそうです。宿の従業員が『危ないからバス停までついていってやる』って言ったらしいんですけど、その女の子は『すぐそこだからいいわ』って断ったらしいんですよ。そしたらやられちゃって。」
「そりゃ辛いな。」
僕もまず何も持たずにふらりとホテルの近く、タウン中心部を歩いてみた。すぐに男が声をかけてくる。
「ケニアのお土産マーケットがそこにあるんだ。僕が案内するよ。」
「いや、いいよ。そこのスーパーでタバコを買うんだ。」
強盗や引ったくりは当たり前、なんていう先入観があると、声をかけてくる奴がすべて悪人に見えてくる。で警戒心もレベル800、って感じでほとんど何も受け付けない状態だ。仕方ない。
その後思い切ってデジカメを持って出てタウンと呼ばれる市内中心部を歩きがてら写真を数枚撮ったが、このナイロビでの大晦日は基本的にホテルのフロント前の小さなロビーで、通りの様子を眺めながら、沈殿したバックパッカーのように終日過ごした。入れ替わりロビーにやってくる従業員やコックや旅行会社の男やホテルの客や娼婦などとしゃべる。彼らは悪人とは程遠い。
ホテルのオーナーのオッさんの兄という、威勢のいいオヤジがフロントにやって来た。サンダルにゆったりとした民族衣装のような服装、彼はフロントのカウンターに座った弟にひとしきり話しかけた。彼は、フセイン処刑を憤っていた。
そう、僕も今朝ナイロビの国際空港内の新聞スタンドで英語紙の朝刊を見て初めて知ったのだけれど、イラクのフセイン元大統領が処刑されたのだ。1面いっぱいに掲載されたフセイン死刑囚の写真と見出しは、僕を愕然とさせた。結局、戦勝国が敗戦国を裁いた東京裁判と同じ。武力が優れた国が、弱い国の人間を殺す。始めから裁判なんかやる気ないのだ。始めから規定路線の死刑まで、形式的な手続きを踏むだけ。こんなことは今さらで、みんなかねがね思っていることだと思うけど、何で日本のA級戦犯だけが死刑になって、数十万の無実の民を原子爆弾によって虐殺したアメリカ大統領が死刑にならないのか?なぜなら、アメリカが戦争に勝利したからである。結局戦争に勝ったか負けたかでしか物事が判断されないのだ。裁判は形式的に国際法に照らし合わせて有罪・無罪を決定すると言っているが、そんなものは詭弁で、国際法違反であれば真っ先に死刑になるのは、原爆を落としたアメリカ大統領であるはずである。
ホテル支配人の兄のオッさんは、アメリカの非道を強い語気で糾弾する。
「アメリカってのはメチャクチャだ。」
「そうですね、自分の気に入らない国に言いがかりをつけて侵略し、やりたい放題。本当に昔から同じことばかり繰り返している。」と、僕は同調した。
「ブッシュはいつかこの報いを受けるさ。」
「あなたはイスラム教徒ですか?」
「いや、違うよ。」
この兄も、ホテルオーナーの弟も、キリスト教徒だという。だが宗教に関係なく、誤っていることは誤っているのだ。それを判断できる人がアメリカにはいないのだろうか?といつもながらの疑問に当たりつく。
兄のオヤジは自分の部屋に戻っていった。僕は改めてホテルオーナーの気難しい顔をしたオッさんと話し始める。
「ケニアはキリスト教徒の方がイスラム教徒より多いですか。」
「そうだな。だが俺には2人の妻がいる。さっきの俺の兄貴には12人もいるよ。」
「えっ、12人ー?あなたキリスト教徒でしょ?」
「まぁそれは宗教とは関係ないさ。金持ちが扶養するのさ。」
「あなた、金持ちってことですね(笑いながら)。」
イスラム教では一夫多妻は普通である。ただし、現実には複数の妻、さらに多くの子供たちを扶養していくだけの財力がなければ無理だというのは、エジプトでフルーカに乗って夕方のナイル川の日没を眺めながら船頭のオッちゃんに聞いたことである。
このホテルオヤジはキリスト教徒なのに。モルモン教くらいだよね、一夫多妻を認めてたのは。
ここナイロビの町にも巨大なモスクがある。ケニアでは比率的には圧倒的にキリスト教徒の方が多いとはいえ、イスラムの影響もかなりあるようである。この一夫多妻の状況はそれを如実に表しているような気がした。
ホテルの従業員、ベンソンは気のいいオヤジである。彼はさっき僕の部屋の鍵が開かなくなったのを、直してくれた。鍵穴がイカレて、鍵を挿入しても回せなくなったのだ。彼はドアの上の狭いガラス戸から部屋に入り込み、中から開けてくれ、さらに鍵穴を応急修理してくれた。仕事の合間、彼はロビーで通りを見ながらのんびりしている。
彼に一番の懸案事項であるナイロビの治安を聞いてみる。
「ナイロビって街は危ない街だろう?」
「そんなことないさ。普通だよ。」
「(『歩き方』を見せながら)だけどこの旅行ガイドブックには、『危ないから出歩いちゃいけない』って書いてある。」
「そんなバカな。だって、外見てごらんよ、みんな歩いてるだろう?」
「いや、そりゃ地元の人は大丈夫なのかもしれないけど、旅行者は狙われるんじゃないの、強盗に。」
「そんなことないって。そんなこという奴は初めて見たぞ。」
ベンソンは、ホテルオーナーの気ムズカシ顔のオヤジに振る。
「ナイロビは危ない街じゃないよな?」
「治安は普通の街だよ。」
(ビビリすぎか。実際にはそうでもないのかな。)
すると、一人の黒人がやって来た。黄色い野球帽をかぶってジーンズをはいている。ひょろっと背が高く面長。その輪郭が、典型的な黒人とは違う印象を語っている。彼は僕の隣に座りオーナーに向かって何やらまくし立てている。
彼はソマリア人で、今隣国エチオピアとの紛争が激化していて、今日はナイロビでこの紛争調停に関する国連との会議でソマリア政府代表団と一緒に来ているらしい。僕は彼に詳しい話を聞いてみた。キリスト教国のエチオピアとイスラム教国のソマリアはここのところ紛争が絶えず、アメリカが肩入れするエチオピア軍によってソマリアは再三攻撃を受けているそうである。紛争の元はよくある領土問題らしい。ある地域の領有権を双方が主張して激突が繰り広げられているらしい。僕が持っていた東アフリカの地図を使って、彼は都市を指差しながら説明してくれた。彼は政府関係者だというが、どうみてもその格好はそうは見えない。どちらかというとみすぼらしい服装である。この先にあるインターコンチネンタルホテルで会議は行われているらしい。
彼もアメリカのあこぎさに憤慨していて、その部分では僕も大いに同意した。30分くらい一通り話して、僕はいったん部屋に戻るといって立ち上がると、彼はロビーの裏までついてきて、こう言った。
「なぁ、君を友達と見込んで、頼みたいことがあるんだ。」
「何だい?」
「僕は今友人をこのロビーで待っているんだけど、なかなか現れないんだ。インターコンチネンタルホテルまでのタクシー代をちょっと貸してほしいんだけど。」
(やっぱりそうくるか、どう見ても何かおかしいと思ってたんだよなー)
「いや、断る。」
「そうか、ならいいんだ。」
彼はさびしそうに去っていった。
このホテルの二階にはレストランがある。レストランから、一人の若者が僕に声をかけてきた。
「あなたはニャマ・チョマを食べたいんだって?」
「あぁ、そうなんだけど、このあたりのレストランにはないんだよ、ニャマ・チョマ。」
ニャマ・チョマというのはケニア風焼肉で、ケニアでは代表的な食べ物である。実はさっき、この辺りでニャマ・チョマを食べられるレストランがないかベンソンに聞いて、近くにある数件のレストランを回ったのだが、どこにもなかったのだ。この辺りは観光客向けとか西洋風のレストランばかりな上、今日は大晦日の日曜で結構閉まっている店も多かった。この若者は、それを伝え聞いたレストランのコックだった。
 ホテルのフロントにある巨大なアフリカ地図時計 |
「僕が今晩作ってあげるよ。」
「本当か?頼む。」
「今から買出しに行くから、午後7時くらいでいいかい?」
「いい、いい、感謝するよ。」
このホテルエンバシーには、怪しげな女性が出入りしている。彼女らは、二階のレストランで昼間から数人でダベっている。ロビーにいた僕にも一人の中年の女性が、怪しい視線と意味ありげな笑顔を投げかけてきた。彼女は、優しげな笑顔としとやかな雰囲気を持っていた。
「あなた、昨日街であたしと会ったわね?」
「そんなまさか。だって俺ナイロビに来たの今日の朝ですよ?」
「いいえ、あれは絶対にあなただったわ。」
と彼女は言い張る。
ベンソンらホテルの従業員は黙ってこの会話を聞いていたが、どうも彼らはこの女性を無視する雰囲気があったので、僕はようやく気づいた。そういうことね。娼婦ね。確かに中年の割にはかわいげな雰囲気を持ったオバちゃんだ。
そんなこんなでロビーでいろいろな人間と話をし、道行く人々を眺めているうちに日は暮れていった。ナイロビの街にほとんど外出することもなく。
夜8時。僕は満を持して二階のレストランへ行った。もうニャマ・チョマが出来上がっているころだろう。ウェイトレスの女性に事情を話して、席で待つ。すでに例の娼婦のオバちゃんは、同僚のオバちゃんと一緒にテーブルで何かを飲んでいた。盛んにこっちに目配せをしてくる。うぅぅ・・・。もっと若くてかわいい娘だったらいいのに・・・。と内心もやもやしつつ、彼女らを完全無視する。
オバちゃんは、「こっちの席に一緒に座らない?」と僕を誘ったが、答えはもちろんNO。
コックの若者は厨房で作っている最中らしい。15分ほど待って、ようやくニャマ・チョマが出てきた。若者は顔を見せない。運ばれてきたニャマ・チョマは、僕が想像していたものとはだいぶ違っていた。『歩き方』に載っているニャマ・チョマの写真とは異なっている。見たところただの焼肉にしか見えない(右写真)。僕はウェイトレスの女性に念を押した。
「これがニャマ・チョマ?」
「そうです。」
「本当に?」
「えぇ。」
食べてみるとやっぱりただの焼肉だった。これならどこででも食べられそうだ。っていうか僕でも作れそうだ。僕はガッカリしながら肉を口に運ぶ。食べ終えてカウンターで金を払う。肉に米、サラダのワンプレートで300Ksh(約4.5ドル)。コックと話をした時には250Kshで交渉成立していたので抗議したが、メニューを見せられて言いくるめられてしまった。不本意だったがせっかく作ってくれたんだからしゃーないか、としぶしぶ払った。するとレストランに例の日本人バックパッカーの若者がやって来た。軽く言葉を交わしてフロントへ。明日の朝のタクシーを頼んでいると、若い女が入ってきて僕に何やら話しかけてきた。フロントのオッちゃんは、僕に向かって「そいつに構わないで、早く戻れ。」と合図を送ってきた。若い娼婦は、「マッサージいかが?」と僕に言ったようだが、僕もその気はないので無視して部屋に戻った。娼婦たちには大晦日だろうが関係ないんだろうな。生活のためだもんな。旅行者が多いからホテルでの出張営業にはかき入れ時なのかもしれない。
大晦日の夜。そういえばこのホテルに来たときに、タクシーの運ちゃんに、カウントダウンのパレードに連れて行ってやる、と誘われたが、お話にならないくらい高い金を要求されたので断った。年越しのパレードはそりゃもうとんでもない賑わいで、花火が豪快に上がるんだ、と奴は言っていたので、部屋で外の街の物音に耳を澄ますが、年末の喧騒は何一つ聞こえてこない。祭りが行われるのは確かボーマス・オブ・ケニアとかジラフセンターの方だと言っていたから、きっとここからじゃ聞こえないんだろう。夜は更け、12時になるだいぶ前に早々に眠りに落ちた。思えば年越しの瞬間、1月1日の午前0時に起きていないことは滅多にない。だが海外旅行しているときは朝が早いことが多いので眠っていることもある。年越しの瞬間に眠っていたのはインドに行った4年前以来のことだろう。
元旦の朝。2007年はいつの間にかやって来た。蚊帳は吊ったが蚊もいなく快適に眠れた。
朝食は込み、2階のレストラン。オーソドックスな内容。パン、ジャム、卵、コーヒーにジュース。タンザニアと違い、スクランブルエッグには塩味がしっかりついていた。
いよいよ今日から3日間、マサイ・マラ国立公園でのサファリである。
ホテルエンバシーのチェックアウト時、親しくなったベンソン、従業員の若者と別れを惜しむ。彼らは「たった1泊でもう行くのかよ?」と言うが仕方ない。彼らに写真を送ることを約束し、連絡先を聞いて、タクシーに乗り込む。ホテルからタクシーで、国内線の小型機が発着するウィルソン空港へ向かう。昨日ホテルのフロントで頼んでおいたのだけれど、価格交渉は難航。あまり下がらなかったが、どのくらいの距離か分からないのでしょうがなく合意。だが空港は近かった。失敗したーと思ったのもつかの間、小型飛行機が発着する様子を見ているうちに、これから行く先で見ることができるであろう光景を思い浮かべてワクワクしてきた。
空港の駐車場で働く係員と、タバコを吸いながら会話する。彼は日本に多大な関心を持っていて、ことに車や家電製品といった日本の技術力に敬意を表していた。僕が電機メーカーで働いていると言うと、「今度携帯電話を送ってくれ!」と笑いながら言う。
「車でも家電でも、日本製品は高いけれどベストだ。」
午前10時。飛行機はナイロビを飛び立ってマサイ・マラ国立保護区へ出発した。
(次へ)
(戻る)
(アフリカ旅行2006-2007 1−2−3−4−5−6−7−8−9)